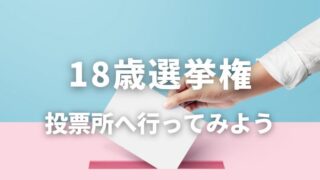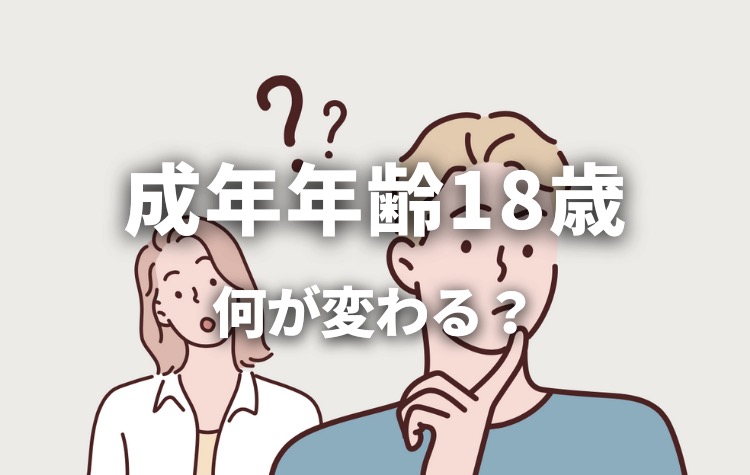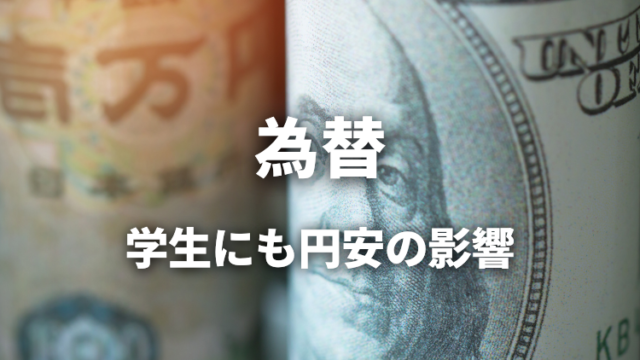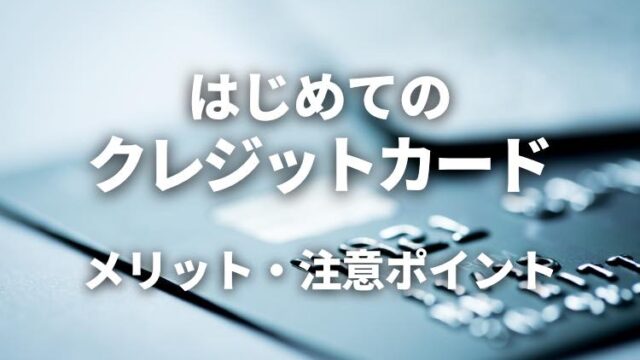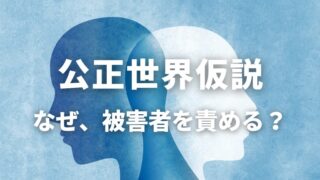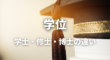民法の改正で、2022年4月から成年年齢が20歳⇒18歳に引き下げられます。今後は、原則すべての大学生と高校3年生の一部は「大人」として扱われます。しかし、これまで「20歳から」となっていたことが何もかも「18歳から」になるわけではありません。何が変わって、何が変わらないのか。この記事では、成年年齢の引き下げを、「法律」に注目しながら解説します。
「成年年齢の引き下げ」は民法の改正によるもの
2022年4月から成年年齢が引き下げられ、18歳以上が成年(大人)として扱われることになりました。
「成年」とは法律上の「大人」のこと
そもそも「成年」とはどういう意味でしょうか。成年は、日常的にはあまり使わない言葉ですが、法律上の「大人」のことです。そして、法律上の大人(成年)とは、①一人で有効な契約を結べる②父母の親権に服す必要がない、という人を指します(詳しくは後で説明します)。
普段の会話で「大人」というと、精神的、肉体的に十分に成長している人を指しますが、法律上の大人=成年にはそのような意味はないことを覚えておきましょう。
では、いつどのように成年年齢の引き下げが決まったのでしょうか?
決まったのは2018年6月です。すべての法律は、国会で審議して可決することで成立します。成年年齢に関しては、「民法の一部を改正する法律」という法律が成立して、この中で第4条の「『二十歳』を『十八歳』に改める」と決定しました。
また併せて、民法第731条の婚姻年齢(結婚年齢)も、これまでの「男性18歳、女性16歳」⇒「男女共に18歳」に改正されることが決まりました。2022年4月1日以降は、男女共に18歳以上で結婚が可能になります。
改正されるのは「民法」ですが、そのためにまず「民法の一部を改正する法律」を国会で成立させるという、独特の仕組みになっています。ちなみに、「民法」とは財産と家族関係に関わる基本的な法を扱っている法律のことです。
成年年齢の引き下げは、今から15年前に検討されていた
実は、成年年齢の引き下げの検討が始まったのは、改正の法律が成立する2018年より10年以上も前のこと。2007年5月に「憲法改正に関する国民投票法」が成立し、満18歳以上にその投票権があるとされましたが、その法律の「附則」(本則に付随して必要なことなどを記した部分)に次のような記載があります。
(条文の引用)
満18歳以上満20歳未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
つまり、今から15年前には、すでに公職選挙法や民法で年齢の規定を検討するようにという案が出ていたということです。
成年年齢に先立って、2015年には「公職選挙法」が改正され、選挙権年齢は「20歳以上⇒18歳以上」に引き下げられています。民法の改正もこの流れに沿ったもので、その背景には成年年齢を引き下げることで、若者の積極的な社会参加を促そうという国の考えがあります。
世界では18歳以上を成人とする国が多数
また、世界の多くの国で18歳以上を成人としていることも、成年年齢が18歳に引き下げられる理由のひとつです。例えば、経済協力開発機構(OECD)加盟38カ国では、ほとんどの国が18歳を成年年齢としています。
成年になると、自分一人で有効な契約が結べる
18歳から大人として扱われることで、これまでとは何が変わるのでしょうか。
民法第5条では、「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」と定めています。法律行為は「契約」と読み替えることができ、また法定代理人は主に親権者(父母など)を指します。
さらに、民法第818条では「成年に達しない子は、父母の親権に服する」と定めています。これは、未成年の間は親の監護・教育のもとにあるということです。
両方をまとめると、「18歳以上は、親の許可を得なくても自分一人の意思でさまざまな契約を結べるようになる」ということができます。
クレジットカード、携帯電話、一人暮らしの部屋も契約できる
具体的には、
- クレジットカードを持つ
- 携帯電話(スマートフォン)を契約する
- 一人暮らしの部屋を借りる
- 高額のローンを組む
といったさまざまな契約を、親の同意がなくてもできるようになります。ただし、実際の契約では、収入要件などがあり学生は契約できない場合もあります。
なお、厳密には日常の買い物でもその都度「売買契約」を結んでいることになっています。未成年であっても、小遣いや仕送りの範囲で行う日常の買い物などの契約は、保護者の同意は必要ありません。
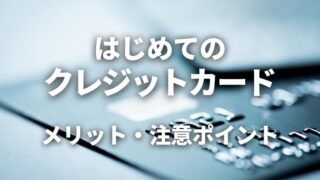
未成年取消権も適用されなくなることには注意!
親の許可を得なくても、自分一人でさまざまな契約ができることは魅力的な反面、注意も必要です。未成年者の間は、未成年者取消権(民法第5条の2項)があり、親が同意していない契約については後から取り消すことができました。
例えば、「高額商品のローンを親に黙って組んでしまった」という場合、これまでなら18歳、19歳の人は未成年者取消権によって、契約の取り消しが可能でした。しかし、2022年4月以降は18歳、19歳が結んだ契約は、未成年者取消権を利用することができないため、片方の都合で一方的に取り消すことはできません。新たに「成年(大人)」として扱われる18歳、19歳の人は、契約を結ぶ前に特に慎重になる必要があります。

成年年齢の引き下げに伴い、18歳からできるようになることは?
2022年4月以降、18歳からできるようになることは「契約」だけではありません。「民法」の成年年齢は、民法以外のさまざまな法律でも「基準」とされています。そのため、成年年齢の引き下げに伴い、これまで20歳以上とされていたことの一部が18歳からできるようになります。
「できるようになること」の中で、もっとも多くの人に関係がありそうなのは、パスポートの有効期間でしょう。これまでは、20歳未満が取得できるパスポートの有効期間は「5年」でした。しかし、今後18歳以上は10年間有効のパスポートを作れるようになります。また、公認会計士や司法書士、行政書士などの資格を取得できる年齢も、これまでの20歳から18歳に引き下げられます。
これまでどおり「20歳から」で変わらないこととは
成年年齢が引き下げられても、これまでどおり「20歳から」というものもあります。例えば、
- 飲酒
- 喫煙
- 競馬
- 競輪、オートレース、ボートレース
などで、これらは健康面への影響やギャンブル依存症の対策といった観点から、現状と変わらず20歳未満は許可されません。
また、飲酒や喫煙などとは意味合いが異なりますが、国民年金基金への加入義務もこれまでと変わらず、20歳からです。他にも、
- 自動車の大型・中型免許を取得する
- 養子を迎える
- 猟銃を所持する
などは、いずれも以前から20歳以上で、成年年齢が引き下げられても変更はありません。
ちなみに、成人式については法律とは関係のない行事なので、今後も多くの自治体では20歳を対象にして開催されるようです。
パチンコ・パチスロはもともと18歳以上ならできる
では、パチンコやパチスロはどうでしょうか。実は、パチンコやパチスロはもともと18歳以上なら利用できます。根拠となっている法律は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)です。この法律の「禁止事項」に「十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること」とあるため、以前から18歳以上は利用OKということになります。
ただし、各都道府県の「青少年健全育成条例」や各高校の校則によって、18歳以上でも高校生はパチンコ・パチスロ店には入店禁止となっているケースがほとんどです。また、店側の自主規制で高校生は入店不可ということもあります。風営法上では問題がなくても、「18歳以上なら大丈夫」と思わないようにしましょう。
なお「条例」とは、都道府県や市町村などの地方公共団体が、地方自治法に基づいて制定した「自治立法」のことです。国会で成立した「法律」ではありませんが「法」のひとつです。「法」はその国で強制力を持った規則のことで、違反した場合には罰則などがあります。
成年年齢引き下げは、民法以外の法律の記載にも影響
パスポート取得や公認会計士や司法書士、行政書士などの資格、飲酒や喫煙の可否については、民法とは異なる、別の法律によって定められています。それらの法律でも成年年齢の引き下げにあわせて修正が必要となったものもある一方で、修正されずに以前のままのものもあります。
「旅券法」は改正されても、「公認会計士法」は改正されない理由
パスポートに関わることは、「旅券法」という法律で定められています。また、公認会計士は「公認会計士法」、司法書士は「司法書士法」、行政書士は「行政書士法」など、それぞれ管理する法律が定められています。
いずれも年齢に関しては、20歳⇒18歳に引き下げられますが、ここで挙げた中で法律が改正されるのは、「旅券法」のみです。その理由は、旅券法にはパスポートの有効期間が5年となる人の要件として「二十歳未満の者である場合」としているからです。そこで、2022年4月1日からは、「旅券法」のこの部分は「十八歳未満の者である場合」に改正されます。
一方、「公認会計士法」や「行政書士法」では、公認会計士や行政書士になる資格を有していない者として、以前から「未成年者」と明記していました。この表記なら、未成年者が20歳未満から18歳未満になっても表記を変える必要がありません。
飲酒や喫煙は法律名が「未成年」⇒「二十歳未満」へ変更
逆に、これまでどおり「20歳から」で変わらない場合であっても、法律の名称や条文の表記に改正が必要になるケースもあります。具体的には、「未成年」は「二十歳未満」に変更する必要があります。
未成年の飲酒は、「未成年者飲酒禁止法」という法律で禁止していますが、未成年=18歳未満となってしまうため、法律名が「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」に改正されます。喫煙も同様で、法律名が「未成年者喫煙禁止法」⇒「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」に変わります。
また、競馬や競輪、オートレースなどの公営ギャンブルは、それぞれの法律の中で「未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない」のように「未成年者」と表記しています。そのため、それぞれ「未成年者」⇒「二十歳未満の者」に改正されます。
つまり、これらの法律で「未成年」という表記のままにしておくと、「18歳から飲酒もギャンブルもOK」ということになってしまうので、それに対応するために「二十歳未満の者」と修正する必要が生じたわけです。
行動する前に年齢要件を確認しておけば安心できる
繰り返しになりますが、成年年齢の引き下げでまず気を付けるべきは「契約」です。2022年4月以降、18歳以上が結んだ契約は保護者が取り消せないということをよく理解して、安易な契約はくれぐれも避けるようにしましょう。
また、成年年齢の引き下げに合わせて、18歳に引き下げられものもあれば、20歳以上のまま変わらないものもあります。しばらくは混乱することもあり得るので、迷ったときには必ず公的なサイトなどで正しい情報を確認するようにしましょう。
法律の条文は、とっつきにくいイメージがありますが、現在、徐々に口語でわかりやすい文体に改められつつあります。気になった法律があれば、デジタル庁の「G-GOV 法令検索」を利用してみるのがおすすめです。日本の法律や法令を検索して表示することができます。
・G-GOV 法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/
参考
・18歳から“大人”に! 成年年齢引下げで変わること、変わらないこと
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html